 金属の強度試験
金属の強度試験 試験片による強度試験:アルミニウム合金鋳物(AC7A)の引張試験
引張試験は金属材料の強度を評価するために行う強度試験の1つです。製品材料の強度確認、製品そのものや不具合品の強度確認をすることもあります。引張試験の概要とJISの標準試験片によるアルミニウム合金鋳物(AC7A)の引張試験について説明します。
 金属の強度試験
金属の強度試験  はじめての音振
はじめての音振  航空機の実機試験
航空機の実機試験 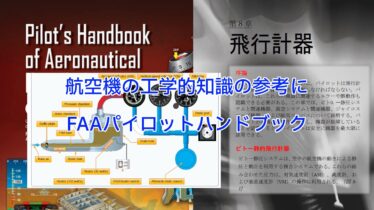 航空・宇宙のモノづくり
航空・宇宙のモノづくり 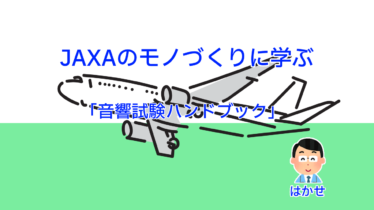 航空・宇宙のモノづくり
航空・宇宙のモノづくり 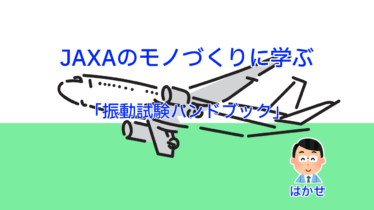 航空・宇宙のモノづくり
航空・宇宙のモノづくり 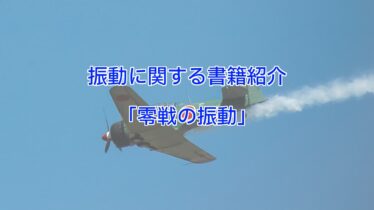 振動騒音の計測と対策
振動騒音の計測と対策 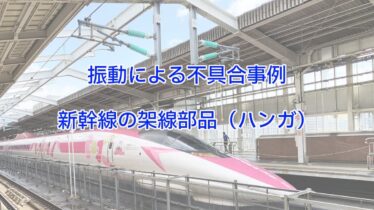 振動騒音の計測と対策
振動騒音の計測と対策  航空機の実機試験
航空機の実機試験  航空機の実機試験
航空機の実機試験